事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
「選任」して終わりではありません。所轄の労働基準監督署長への届出まで必要です。
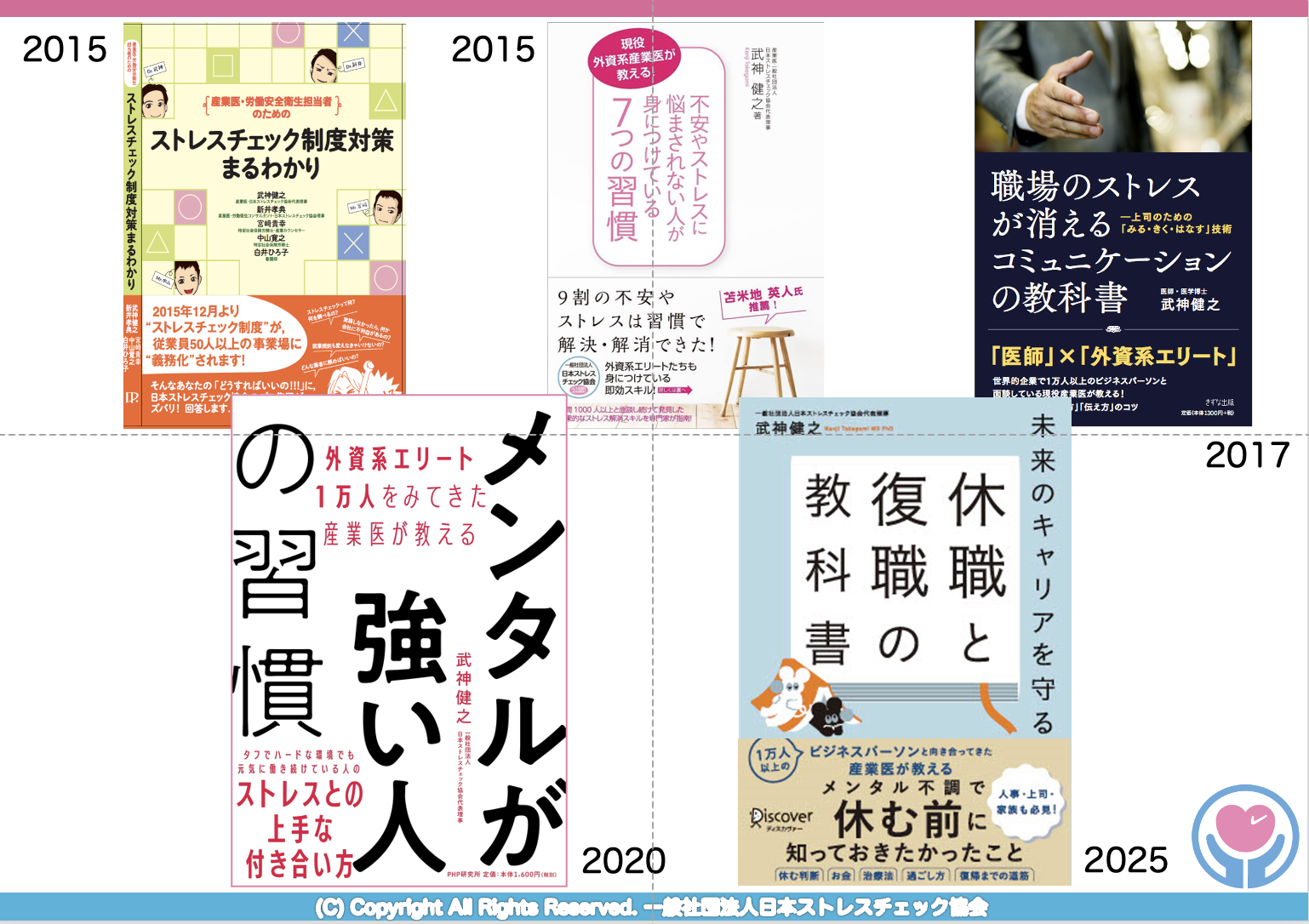

労働安全衛生管理と産業医活動は、決して難しくありません。 正しい知識を持って実践すれば、従業員の身体と心の健康の実現だけでなく、企業経営側のリスクマネジメントとしてもお役に立ちます。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
「選任」して終わりではありません。所轄の労働基準監督署長への届出まで必要です。
いい産業医は、必ず、現場(会社)に行きます。
現状について時間をかけて話に耳を傾け、最適な具体案を提案していきます。
いい産業医は、従業員の面談においても、何でも相談できる雰囲気を心がけます。
プライバシーに関わることも多いですので、秘密厳守はいうまでもありません。
いい産業医は、会社との相談事においても、経営者の立場を理解しようと心がけます。
多少、経営者には耳の痛いことも言うこともありますが、その会社を理解することに勤めているはずです。
そして、何よりも、
いい産業医は、「コミュニケーション」が上手な産業医だと思います。
企業内産業保健サービス(企業の健康管理)に関する問題は、表面に見える状況は似ているようでも、ひとつひとつ原因が異なります。
ある程度のマニュアル的なものはありますが、それでは根本的な解決には至りません。
決して一言で簡単に言えるほど、単純なものではないのです。
そもそも普段は病人を診察していることが多い街の開業医の先生や病院の先生たちと、企業内で会社のリスクマネジメントの立場からいろいろな活動をする産業医とでは根本的な違いがあります。
産業医の取り扱う業務が多様化する中で、産業医一人に全てを任せるのではなく、企業の衛生管理者やアウトソーシング機関等との連携による業務が最近増えてきています。
さらには今後、複数の専門分野の異なる産業医が事業場の衛生管理等を行うことが、より効果的であるケースもあると考えらます。
こうした「チームワーク」を理解し育てられる産業医は、いい産業医だと思います。
下記の目安をご参照下さい。
実際は、名義貸しや社員の定期健診提携先医療機関による掛け持ちの場合はもっと安くなっていると思います。
衛生委員会の参加資料の作成や、積極的に会社の従業員の健康管理に参加を心がけている先生などはもう少し高めの印象です。(そういった先生は口コミでしか探せないことが多いです。)
安くてもいい産業医もいます。
しかし、安かろう、悪かろう・・・。世の常です。
(もちろん、高くても悪い産業医もいます。)
貴社の産業医の適正(相場)価格は?
実際にどのように選任するのか?
二人目の産業医が必要か?どのような産業医か?
等、サイトで扱われていなことなど、どんな些細なことでも結構です。
管理人が責任を持ってお答えさせて頂いております。
相談は無料です。また、メールによる相談は匿名でもかまいません。
産業医.comでは皆様のからのご質問、ご意見、ご感想等を参考に、最良の提案、サイトの改善を心掛けております。
産業医の選任・メンタルヘルス・過重労働・安全配慮義務・是正勧告など、産業医の関する業務でお悩みの会社の担当者様は、お気軽にお問い合せ下さい。
ご提供頂いた個人情報は、産業医.comのプロモーション及びお客様への情報提供に使用するもので、第三者に開示・漏洩することはありません。
なぜ過重労働対策が必要なのでしょうか?
過労死の背景には、高血圧・糖尿病・高脂血症といった生活習慣病と、うつなどの精神障害を認めることが多いです。
従来このような病気は、「従業員個人の私病」で「自己管理責任」であると考えられてきました。
しかし近年は、
「業務に直接起因しているとはいえないが、業務と密接な関係を有する健康障害」
=「過重な労働負荷」
により生じた健康障害であれば、「事業者にも」責任があるのではないかというように考えられるようになってきています。
業務に直接起因とは、例えば粉塵作業とじん肺、アスベスト被害。有機溶剤や鉛等の業務とその疾患などです。
業務と密接な関係を有する健康障害とは、
例えば、
残業時間が多い→(食生活が不規則)→生活習慣病になった、労働環境がよくない→(ストレス多い)→うつになった、などを意味します。
そのような具合で最近は、
法定の健康診断(つまり会社の健診)で把握できる作業関連疾病の管理(生活習慣病も含む)
にも事業者、更に管理監督者への責任が課せられるようになりました。
よって、会社は従業員の健康状態だけでなく、残業問題も把握する必要があります。
(ちなみに、管理職・裁量労働制であっても、労働時間管理が必要です。)
労災補償に際して、精神疾患の認定の基準は以下の3点と考えられます。
1. 精神障害を起こしていた事実
2. 発病前の半年間に仕事による強いストレス(心理的負荷)があった
強いストレスとは、
仕事の失敗、過重な責任の発生、仕事の量・質の変化(勤務の長時間化)、
身分の変化(退職の強要)等を指します。
3. 仕事以外のストレスや個人的事情で精神的障害を発病したとは思われない
例えば、離婚や別居。
ほかに配偶者や子どもの死といった出来事との関連性がないことなどです。
・残業の削減、労働時間の適正管理
Ø 残業は月45時間以下にするよう、努力。
Ø 就業日ごとの始業・就業時刻をタイムカードなどで記録、確認。
・年次休暇の取得
Ø 年次休暇を取得しやすい職場環境づくりをし、取得促進。
・健康診断の実施の徹底と事後措置
Ø 年1回の定期健康診断受診を徹底。
Ø 深夜業務がある社員には6ヶ月内に1回の特定業務従事者健診を実施。
Ø 有所見者については、医師の意見を聞き、必要な事後措置を行う。
そして、最近の“はやり”が、
・残業時間の多い社員へ産業医による保健指導等の実施。いわゆる過重労働対策面談です。
Ø 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
事業者は、面接指導の結果の記録(疲労の蓄積の状況その他心身の状況、聴取した医師の意見等を記載したもの)を作成し5年間保存します。必要に応じて事後措置を講ずることもあります。
このような状況にならないためには、企業は従業員を残業させない仕組みを考える必要があります。
簡単なことではないかもしれませんが、まずは、この法律を頭の片隅に置いて、従業員の日々の働き方を再考して下さい。
残業を減らすことは工夫できる場合があります。
例えば、ノー残業デーをつくるなどです。
この結果、業務効率が上がり、残業が減った例も多くあります。
ほかに、過重労働面談の実施を従業員に通知したことにより、
それだけで、従業員の残業時間が減った例もあります。
きっと、「先生」との面談によほど抵抗があったのかもしれませんね。
長時間働くことは美徳ではありません。
組織全体の作業効率を上げることも仕事です。
時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、事業者はその労働者に対し医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
この面接を、過重労働面談といいます。
実施しなければ法律違反です。
この時、産業医は主に2点について注意しながら面談を行います。
まず、健康障害がないか?
直近の健診結果も併用します。
次に、うつ病の気配はないか?
疲労やストレス調査票などを用います。
事業者はその後、面談を実施した医師からの意見聴取を行い、結果の記録を作成し、これを5年間保存することになっています。
そして、場合によっては、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの事後措置、つまり労働条件、労働環境の改善を実施する義務があります。
ちなみに、時間外・休日労働時間が1月当たり80-99時間で、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合には、面接指導を実施するように努力する義務があります。
つまり厳密には、実施しなくても、法律違反にはなりません。
ここらへんをどのように対処するのかは、会社によりわかれます。
会社のスタンスの違いです。
自分の会社ではどうなっているのか、どうしたいのか、どうするべきか。
あなたの社内でご検討下さい。
近年、企業内産業保健サービスにおいて重視すべき課題としてメンタルヘルス対策があります。
2006年の「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケートによると、
最近3年間における「心の病」は6割以上の企業が「増加傾向」と回答し、過去2回の結果と比較すると、一貫して増加しています。
心の病が増加傾向と答えた企業は?
2002年:48.9%、2004年:58.2%、2006年:61.5%と増加傾向にあります。
メンタルヘルスに関する対策に力を入れる企業は?
2002年:33.3%、2004年:46.3%、2006年:59.2%と、メンタルヘルスに関する対策に力を入れる企業も倍近くに増えています。
さらに、メンタルヘルス対策について、約9割の労働組合が必要性を肯定していることを示したものもあります。(2005年、連合「第5回安全衛生に関する調査」)。
最近のデータでは、2007年度に労働相談情報センターに寄せられたメンタルヘルス(心の健康)に関する相談数は、5946件で、2006年度から105.7%増し、ほぼ倍増となっています。
中でも、「職場の嫌がらせ」が2割増加、また、英会話学校等で働く「外国人関連の相談」も2割増加となっています。
このようなことから、個々の企業、事業場で着実にメンタルヘルス対策が実施されることが求められています。
また、メンタルヘルス不調の労働者が休業から復帰し、又は継続して働き続けられるようにするといった再チャレンジを支援する仕組みについても早急に構築する必要があります。
各社がそれぞれの会社に合わせた、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援プラン」を作成することは、その労働者のみならず会社および人事に関与する人にとって、とても有意義であると思います。
今後とも、こうした対策の実施状況を踏まえて、より効果のあるメンタルヘルス対策について検討していくことが必要です。
1999年9月 「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」
2000年8月 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」
2001年4月 「労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずべき措置に関する基準」
2002年2月 「過重労働による健康障害防止の為の総合対策」
2004年10月 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
2006年3月 「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
実際のメンタルヘルス対策として、「4つのケア」を整えましょう。
1. 労働者個人によるセルフケア
2. 管理監督者による、ラインによるケア
3. 事業場
4. 事業外産業保健スタッフ(事業外業者)によるケア
具体的には、
1. 労働者個人によるセルフケア
・ 労働者自身が、自ら、自らの心の健康のために行う対策です。
・ その内容は、ストレスへの気づき、ストレスへの対処、自発的な相談などです。
・ 実践方法としては、知識の普及や周知のための社内広報(紙・HP)、健康保険組合の雑誌、講習会などがあります。
2. 管理監督者によるライン(職場)によるケア
・ 日常的に労働者と接する現場の管理監督者が行うケアです。
・ その内容は、心身の不調をきたしている部下の把握と相談対応、職場復帰支援などです。
・ メンタルヘルスケアの中で、重要な位置を占めています。
3. 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・ 産業医、衛生管理者、衛生委員会なども含む事業者による、会社としてのケア(への取り組み)です。
・ その内容は、近い問題に対処可能な具体的な計画、経営方針の一部としての中期的計画・予算化などです。
・ 最も重要なことは、事業者による明確な意思の表明=企業としてのコミットメントです。
4. 事業外産業保健スタッフ(事業外業者)によるケア
・ 事業内で足りない部分に関しては、事業外資源の活用などについても決めておきましょう。
・ その内容は、EAP機関などのアウトソーシングや場合により医療機関です。
・ 社内で対応できる範囲とアウトソーシングを使う範囲、関係者のプライバシーの問題などの周知が必要です。
いろいろあって、大変ですが、まずは、必要な時に必要なことができる社内体制を作りましょう。
あなたの会社の人事部、衛生委員会などで、産業医の先生と相談して下さい。