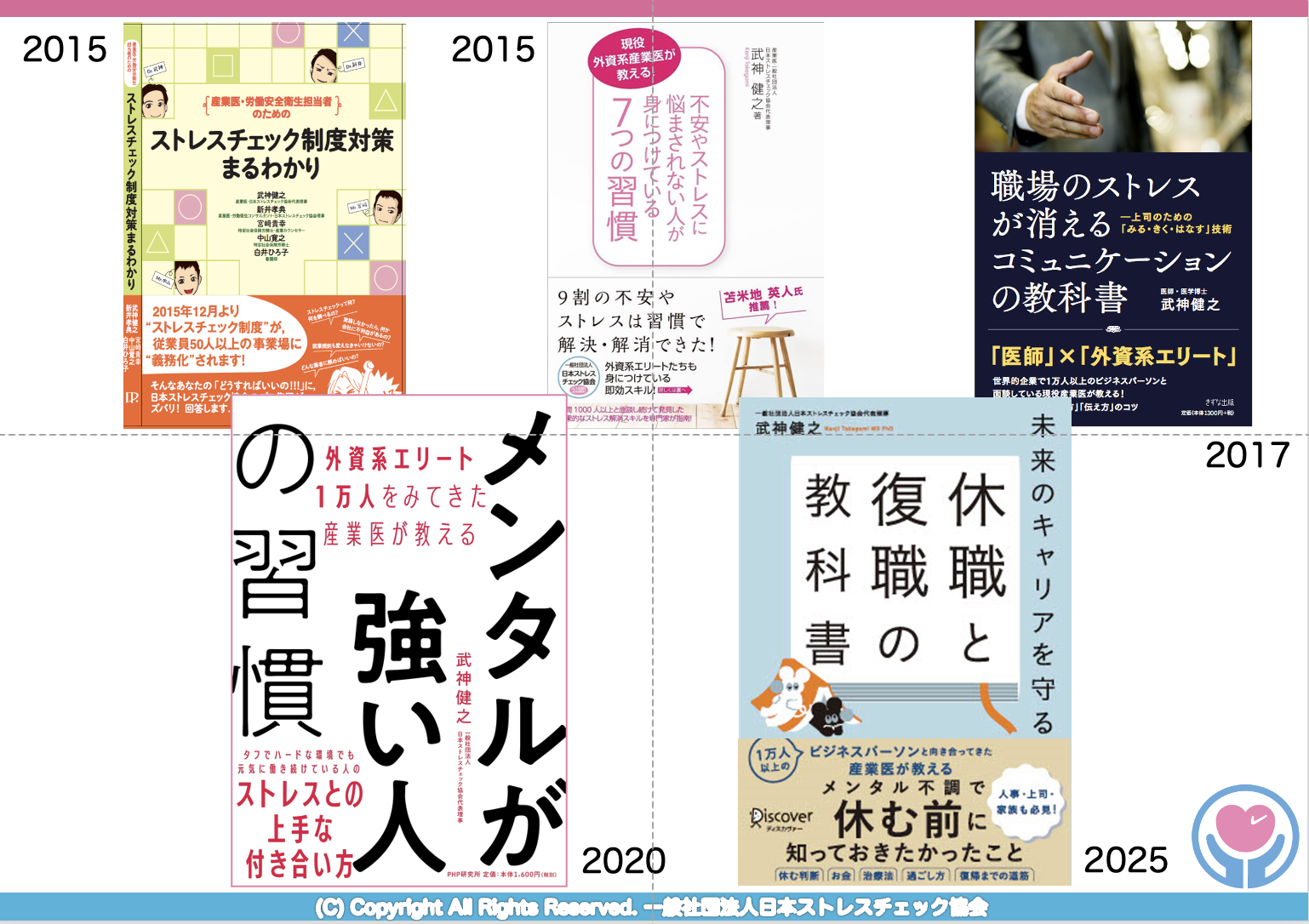今回は、
【所得の低い人ほど、生活習慣に問題がある!?】
という内容のお話しをさせて頂きます。
あなたの会社の労働安全衛生管理・産業医活動のヒントになれば幸いです。
厚生労働省が、平成22年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を、H24.1.31.に報告しました。
これによると、
世帯の所得を3区分(200万円未満、200万円以上~600万円未満、600万円以上)に
分け、年齢、世帯員数を調整したうえで、世帯の所得が600万円以上の世帯員を基準として、200万円未満、200万円以上~600万円未満の世帯員の生活習慣等(体型、食生活、運動、たばこ、飲酒、睡眠)の状況を比較した結果は以下のとおりです。
1.肥満者の割合は、男性では差がみられず、女性では200万円未満と200~600万
円未満の世帯で高かった。
2.習慣的な朝食欠食者の割合は、男性では200万円未満と200~600万円未満の世
帯で高く、女性では200万円未満の世帯で高かった。
3.野菜摂取量は、男女とも200万円未満と200~600万円未満の世帯で少なかった。
4.運動習慣のない者の割合は、男性では200万円未満の世帯で高く、女性では200
万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。
5.現在習慣的に喫煙している者の割合は、男女とも、200万円未満と200~600万円未満の世帯で高かった。
6.飲酒習慣者の割合は、男性では200万円未満の世帯で低く、女性では差がみられなかった。
7.睡眠の質が悪い者の割合は、男性では差がみられず、女性では200~600万円未
満の世帯で高かった。
いつもこの手の話しが出るときに起こる論争ですが、
・所得→生活習慣 なのか、
・生活習慣→所得 なのか、
この相関はいろいろな意見があると思います。
産業医としては、不毛な議論には参加しません。